
オススメの逸品
調査員オススメの逸品 第208回 青春カメラから中高年の相棒へ オリンパスOM-3とOM-3Ti その2
前回の続き。名機OM-3を手にした山下青年とOM-3のカメラ・ライフが幕を開ける。
【一眼レフカメラの進化とOM-3】
OM-3のマルチスポットによって、初めて写真の面白さが分かったような気がした。スポット測光は、表面反射率の問題もあって時に大外れすることもあるが、それはそれで露出を分析的に考えることに繫がる。ところがそれでは万人向きではない。84年から始まったカメラグランプリの第1回は、OM-4とニコンFAの一騎打ちとなったが、たしか一票差位のごく僅差でFAが勝ち取った。撮影者の意思を反映しようとする万人向きではないスポット測光が、何も考えなくても平準的な写真が撮れる万人向きのマルチパターン測光に敗退したと言うことだろう。何か、その後のオリンパスカメラの苦境を暗示するような出来事に思えてならなかった。
その苦境とは、OM-3発売の直後に起こったカメラの世界での大きな変革によるものだ。α(アルファ)ショックと呼ばれたように、ミノルタαシリーズに始まる本格的なオートフォーカス化の流れである。当時5大ブランドと呼ばれていた各社はみな、オートフォーカス化へと舵を切り、システムの一新につとめはじめた。私も各社の動向を注視していたが、市場に出てきたオリンパス製品はカメラ・レンズとも5社の中では最も魅力に乏しく、システムの構築は何とも中途半端だった。これは私だけの印象ではなく、大方の写真ファンの感想だろう。それゆえ、他社がシステムを発展させてゆく中、オリンパスのみがオートフォーカスの市場から脱落し、一眼レフでは数機のマニュアルフォーカス機しか残らないという雌伏期間に入った。そんな中、久しぶりの新製品が94年に登場、このシリーズ最後発になるOM-3Tiがそれで、発売からさほど経たぬうちに購入した記憶がある。
OM-3Tiは、外観は全くといってよいほどOM-3と変わらず、金属ボディが真鍮からチタンに変わり、ロゴにチタンをあらわす「Ti」が付加された程度だが、中身には新たな工夫、進化があった。その一つは、OM-3と同じく機械式の完全マニュアル機でありながら、ストロボのTTLオートを実現していることで、専用ストロボの装着により全速同調も可能になる。ストロボオートはやはりあれば便利で、絵画資料の細部を撮ることなどに活用してきた。
いま一つは、フォーカシング・スクリーンが新タイプに変更され、ファインダーをのぞくとかなり明るく、ピント合わせがし易くなった点である。夕暮れの景観や趣味の舞台写真など、周囲が暗い時の撮影では大いに重宝した。さらに私が感銘を受けたのは、このスクリーンが、旧型モデルにも何の制約もなく取りつけられることで、早速OM-3にも装着した。だが、市場の論理では、フォーカシング・スクリーンの改良や旧モデルへの取りつけ可能などといった、本当に大事なスペックでも地味なものは売りにはならず、本機についての解説やレビューでも、このことを評価した記事はあまりなかった様な印象がある。しかし、日常の撮影ではドラスティックな機能アップよりも、このような細部のリファインの方が有難いし、これまで使用していた機種にまでその恩恵が及ぶことはもっと評価されるべきだと感じている。
自動車でも、マイナーチェンジでほんのちょっとだけデザインをいじって、却ってがっかりさせられることがある。本当に優れたデザインであれば、頻繁に変更すべきではないと言うのが持論だが、OM-3Tiの発表は、その意をますます強くさせた。OM-3・4のシリーズは基本デザインやサイズが変わらず、その中で地道に必要な機能アップが図られてきたという点で、理想的なカメラの進化を見せているように感じられたのである。しかし、世間の大勢は目先の変化を好み、大方の新製品は、デザインの変更によって性能の進化を印象づけようとする傾向が強い。
【OM-3の活躍】
学芸員の世界では、中判以上のサイズで写真が撮れなければ一人前と認められないという風があった。実際、35ミリのフイルムサイズでは、例え低感度フイルムを使用しても、ポスターやA4図録1頁分に使うには些か心許なかったのは確かである。だから、私自身も仕事では、長らく中判のフイルムカメラがメイン機であった。ただ、彫刻や絵画の撮影でも、35ミリカラーポジでおさえておくと、講座・講演などで活用できるという利点もある。また、同じ文化財の写真でも、石造物や社寺景観と言った野外での撮影では、携行性重視でもっぱら小型一眼のOMをメインとしていた。
レンズは35ミリF2.8と85ミリF2からはじめたが、35ミリはのちF2のタイプに買い替えた。写真家で批評家の赤城耕一氏はOMの35ミリならF2.8の方がよいと、書籍や雑誌記事でたびたび書かれており、最新のエッセイ「ボケても、キレても。」では、球面収差によって大きく焦点移動が起こると記されている(『カメラマン』2016年12月号)。ただ私の実感では特に不満を感じたことはなく、大口径の広角レンズの魅力を実感するきっかけとなったレンズである。
その後手に入れた40ミリF2も、画角が肌に合ったようで一時期よく使ったが、ボケの出方にちょっと癖があり、のちにペンタの43ミリF1.9リミテッドを購入してからは、準標準の画角の撮影はこちらが中心になり出番は少なくなってしまった。
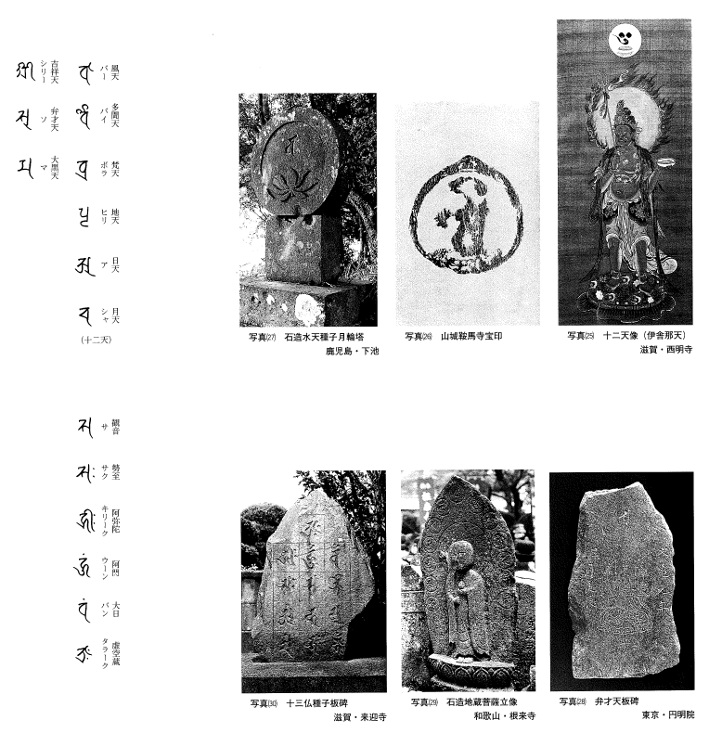
最終的には、50ミリマクロF2、90ミリマクロF2の二本がメインレンズとなった。ともに、当時F2.8から4クラスしかなかった標準・望遠マクロでは最も明るく、それでいて精緻な描写をしてくれた。マクロとしては1/2倍までだが、通常困ることは少ない。調査旅行のカメラケースには、OM2台にカラーポジとモノクロフイルムを入れ、それぞれに50ミリ、90ミリを装着、35ミリをすき間に入れ込み、時に21ミリも加えるというスタイルが確立した。この4本は、いずれもF2で、フィルター径も55ミリと共通しており、操作にも迷うことなく併用しやすい。また、これだけ詰め込んでも、他社のシステムに比べかなり軽量だったのは有難かったが、腰痛のひどい時には、さらに軽量化を図り、OM2台に40ミリと85ミリのセットを持ち出すこともあった。このセットは本当に軽い。それなのにF2と明るく、フィルター径も49ミリに統一できる。OMでは、魅力的なズームレンズがラインナップされなかったこともあり、結局単焦点しか使わなかったが、いま手元にある以上のレンズはすべてF2で、明るいフォーカシング・スクリーンとも相俟って、マニュアルでのピント合わせを楽しむことができた。
つづく・・・
